冷凍空調技術委員会 > 「カーボンニュートラルに向けた先進熱交換技術に関する調査研究プロジェクト」プロジェクト
構成メンバー
学術研究機関側委員 20名
- 濱本芳徳(主査,九州大学)
- 赤坂 亮(幹事,九州産業大学),浅野 等(幹事,神戸大学),井上順広(幹事,東京海洋大学),榎木光治(幹事,電気通信大学),大西 元(幹事,公立小松大学),粥川洋平(幹事,産業技術総合研究所),黒瀬 築(幹事,横浜国立大学),佐々木直栄(幹事,日本大学),巽 和也(幹事,京都工芸繊維大学),角田 功(幹事,静岡大学),斉藤慎平(幹事,産業技術総合研究所),党 超鋲(幹事,福井大学),中村 元(幹事,防衛大学校),廣川智己(幹事,兵庫県立大学),廣田真史(幹事,愛知工業大学),宮崎隆彦(幹事,九州大学),宮田一司(幹事,福岡大学),宮良明男(幹事,佐賀大学),渡辺 学(幹事,東京海洋大学)
企業側委員
幹事 8社, 委員 20社
活動目的
背景
温暖化を抑制するための低GWP冷媒への転換要求に加え,廃熱利用,高温供給,寒冷地対応など,熱源環境は更なる広がりを見せ,これらの冷媒種類や熱源形態に対応した熱交換器の選定や設計が求められている.将来冷媒の方向性は,(1) 低GWP冷媒の使用方法の開発,(2) 自然冷媒の利用拡大,(3) 冷媒の漏洩管理,(4) 微燃性冷媒への対応,(5) 低GWPを優先させたHC冷媒に代表される強燃性冷媒の利用,(6) HFC系冷媒の使用延長の検討など多岐にわたり,それぞれに未解決の問題が多く残されている.今後,新たな低GWP合成冷媒の開発や国際規制の動向に早急に対応する必要がある.一方,近年,オールアルミニウム製空調用熱交換器の開発が進められており,従来銅管の新しい使い方も求められている.一見,従来R&Dの延長のようではあるが,混合冷媒の熱流動特性,冷媒分流,着霜など,解明されていない現象も多く,熱交換器の形態,サイズ,温度状況に応じてそれらの問題が顕在化する可能性もある.
目的
本調査研究では,冷媒動向を調査するとともに,管内外の伝熱促進,高密度伝熱面,冷媒分配,潜顕熱分離空調,伝熱機構解明のための二相流計測と可視化, 冷凍機油の影響などの先進熱交換技術の研究動向について,研究者側委員と特別講師から提供・情報発信し,さらにそれらに関して討議し,熱交換技術の方向性などを検討することを目的とする.
キーワード
熱交換器(Heat exchanger),熱物質移動(Heat and mass transfer),冷媒(Refrigerant),沸騰・凝縮(Boiling and condensation), 気液二相流(Gas-liquid two-phase flow),冷媒分流(Flow distribution),流れの可視化(Flow visualization),伝熱促進(Heat transfer enhancement)
活動内容
年4回×2年間,合計8回の委員会を開催する.
委員会は,研究者側委員や特別講師による話題提供,国際会議や海外滞在研究を通じての当該部門の研究開発における国際動向報告,そして研究者や大学研究室の見学会などで構成する.
- 「CO2を含む将来冷媒の先進熱交換技術に関する調査研究」(2007年~2009年)
- 「将来冷媒の先進熱交換技術に関する調査研究」(2010年~2011年)
- 「将来冷媒の先進熱交換技術に関する調査研究」(2012年~2013年)
- 「冷媒種類など環境変化に対応するための先進熱交換技術に関する調査研究」(2014年~2015年)
- 「環境変化に対応するための先進熱交換技術に関する調査研究」(2016年~2017年)
- 「環境変化に対応するための先進熱交換技術に関する調査研究」(2018年~2019年)
連絡先
日本冷凍空調学会 事務局
吉川 朝郁
TEL:03-5623-3223,FAX:03-5623-3229
E-mail:choiku.yoshikawa.cy[アットマーク]jsrae.or.jp
技術開発の重要度と研究開発完了時期
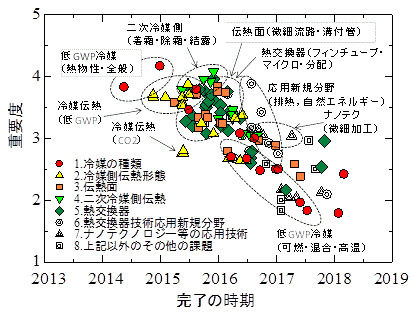
技術開発の重要度と研究開発完了時期(2012年参加企業に対するアンケート結果)
出典:宮良・小山,"冷凍空調用熱交換器に係わる技術課題の調査 -熱交換器技術委員会活動報告-",
冷凍,vol. 88, No. 1025, (2013), pp.215-221.